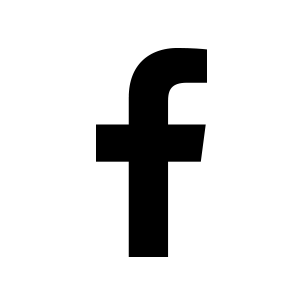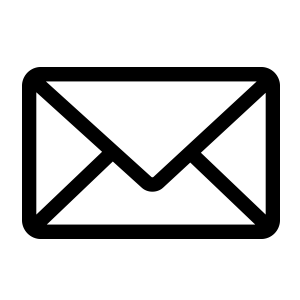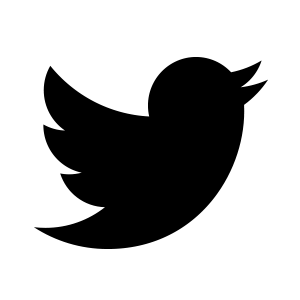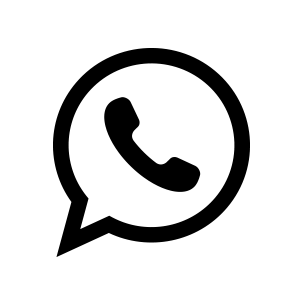voice

Q: ファマリーは、どんな活動をされていますか?
ファマリーは、障害のある人たちによる障害を肯定する劇団です。今回上演するようなミュージカルに限らず、様々な演劇作品をつくっています。様々な特徴のある役者の個性をいかした作品をつくる、言い換えると、様々な特徴のある人たちに創造する機会を提供する劇団です。
Q: True Colors Festivalに参加してみて、いかがでしたか?
本当に素晴らしい体験になりました。True Colors Festivalもそうですし、ホールの職員も親切で、心地よい状況を作ってもらい、本当に歓迎してもらいました。様々な違いを認め合い称え合っていると思いました。
Q: 日本公演で、劇団のみなさんの雰囲気はどうでしたか?
役者は全員それぞれさまざまな特徴があって、たとえば身体障害といわれるものや知的な障害といわれるもの、障害があるといわれる人たちの中でも様々な人、異なる特徴のある人がいるんですが、世界の反対側から来て、違う言葉を話す人たちに向かって私たちが伝えたいメッセージって、実は私たちそんなに違わないよねっていうことでもあると思うんです。ただ、みんなそれぞれの生き方があって、世界へのナビゲーションの仕方があって、そういったそれぞれの体験を日本に来てシェアする。そのことをみんなとても楽しみにしていました。
Q: 公演を客席から見るリーガンさんが誰よりも喜んでいらっしゃって拍手をしていた姿が印象的で愛を感じました。改めて、『ホンク!』どのような可能性をもった作品だと感じましたか?
毎回のことなのですが、作品って観るたびに違う発見があるんです。それはまさに演劇が、生きた芸術表現であるからだと思います。役者たちは生きていて、実際に社会的に阻害された自分自身である感覚というものにすごく正直に舞台に立っている、そんな気がするんです。今回の主人公アグリーも、その本物の気持ちを持った彼が、最後に強い自分自身を見つけられたというのも嬉しかったですし、感動しました。
Q: 原作の『みにくいアヒルの子』では、醜さが環境によってつくられる相対的なものであるということを伝えています。しかし結末では、主人公は、結局多くの人が美しいと認めるような白鳥の子でした。ルッキズムを肯定しているような印象もあるかもしれません。あなたは、もし「ホンク!」でのアグリーが白鳥のように美しい鳥だったとしても、この物語はハッピーエンドになったと思いますか?
今回の舞台制作では、「何が美しいのか?」ということ自体を掘り下げたいという思いがありました。日本でもアメリカでも世界中どこでも「何が美しいのか」に対して人が持っているアイデアって、実はすごく制限されています。原作では主人公が身体的に変容していくという結末ですが、今回の舞台ではアグリーは最初から最後までずっと同じアグリー。実は初めからugly(醜い)じゃなくて、美しかったんだとわかります。つまり、変わったのは主人公の身体ではなくて見る側のマインド。そういう意味での「変容」を、この作品では伝えたかった。人類にとって何が美しいのかというのは、歴史を通しても制限された考え方しか与えられてこなかった部分です。その視点を変えるということを、わたしは自分の作品を通して考えていきたいと思っています。
Q: 確かに、アグリーの変容はマフラーをとるだけで表現されていて、大きな変化ありませんでしたね。
そうです。「みにくいアヒルの子」に限らず、世の中にあふれている様々な物語において、単一化された美しさとは何か、価値のある人間とはどういうものなのか、一つの視点でしか語られないことが多いと思うんです。私たちは、そんな風に矛盾を抱えた原作に挑戦しています。変容することって実はものすごくシンプルで、つまりもともと全ての人に価値があるんだということに、周りの人々が気づくことが重要です。

Q: 鑑賞者の視点を変えるという試みに対して、舞台表現はどんな風に機能しうると思いますか?
パフォーミングアーツの魅力の一つに、人の前に人が立っているということがあります。演劇は物語を語るもので、つまり人の前に立つ人が、自分の人生の意味を語る、作っていく行為だとも思うんです。そういう意味では私自身、事故に遭い体が麻痺してしまったんですが、そのあとに自分の周りのメディアとかTVに映っている人たちをみてみると、自分のような人が全然映っていないということに気づきました。まるで自分が社会の一部ではないように感じました。それで自分にも自信がなくなってしまう感覚も、自分が認められないのではという感覚もありました。パフォーミングアーツというのは、人の前に立つ人たちが多様で、ひとりひとりが素晴らしい才能を持っていることを証明する素晴らしいメディアだと思います。
Q: 舞台で演じている側の人たちを何かの当事者だとすれば、鑑賞者は傍観者であるとも言えると思います。
視点には、自分自身に向けるものだけでなく、他人に対しての偏見も含まれていると思います。私の見解では、多くの人が障害や人と違うことを怖がってしまうのは、ただ単にそれを理解していないからだと思うんです。理解できないからこそネガティブに捉えてしまう。私たちの劇団では、それぞれの特徴をどうやったらクリエイティブに、面白いこととして伝えられるかを考えています。例えば私は車椅子を使っていますが、そういった特徴も含めて自分の身体を楽器のように思っています。楽器ってひとつひとつ、弾き方が違いますよね? だから演奏の仕方を身に付けたら、私にしかできない演奏もできるようになるはずです。自分が自信をもって演奏することさえできれば、他の人もそこに目を開いて、その価値、ユニークであるっていうことは素晴らしいことだと理解してもらえるかもしれない。そして既存の視点を変えるということに開かれた状態であれば、その人の人生の体験はきっとより豊かなものになると思います。

Q: 色々な種類の障害のある人が共にひとつの作品をつくりあげようとする創作の現場において、芸術監督や演出家として意識していることってありますか?
劇団には、本当に様々な特徴のある人たちが在籍しています。まず、どんな作品をつくろうか、どの作品を選ぼうかという時点から、彼らの特徴がいきてくる作品はどれなのか、彼らによって物語のキャラクターたちが生き生きとする作品はどれなのかということを、ぐるぐる考えながら選考しています。
実際にリハーサルに入ってから一番重要なのは、気長であることです。体調を崩してしまったり、移動がうまくいかずに集まる時間が遅れることって、よくあるんです。そういう時に、いつも自分が柔軟に対応できる状況にしておく。演出家としては、作業に入る時に思い描いているビジョンってありますよね。でも実際のリハーサルでは予想もしていないことがどんどん出てくる。最初のビジョンが裏切られるというか、そうやっていろいろ出てくることにどれだけ適用できる状態でいるかっていうのも重要ですね。
様々な芸術表現に言えることだと思いますが、役者は通常作品作りのプロセスに合わせていくことが求められると思うんです。でも私たちは、役者というかそこにいる人間ひとりひとりに対して、プロセスを合わせていきます。そういう意味では、仕事の仕方が根源的に従来とは異なっていると思います。
Q: リーガンさんが描く理想の社会とはどんな姿ですか?またそれを実現するためには、我々は何をすべきでしょうか?
ひとりの理想は、もしかするともう一人の理想の正反対かもしれない。ファマリーという劇団で働いていると、理想的なひとつの社会像を掲げる、イメージすることすら難しく感じられます。人間というのは、だれしもいろんな特徴があっていろんな問題を抱えているものですが、障害ってまさにそれぞれの人間性が凝縮された部分、人間性そのものを増幅させるようなところがあって。障害のある人たちとの仕事では、そういった側面がより拡大された状況にあるという感じなんですよね。だからもしかしたら誰かにとって、誰かの障害にとってはこういう風にするのが一番上手くいくっていうことがあっても、同じ努力がもうひとりの違う特徴のある人にはまったく機能しない、ということもあります。もしかして陳腐に聞こえてしまうかもしれませんが、一番重要なことは、お互いを思いやること。特にアメリカってすごく個人主義な社会で、自分のことしか考えないということがよくあるんです。
だから私にとっての理想が何かということよりも、自分ひとりひとりが可能な範囲でお互い想像し合って助け合って、みんながより楽しく一緒に生きていけるということが、一番理想的だと思います。そういったことを考えた時に、アートもとても重要です。演劇やパフォーミングアーツだけではなくて、美術でも音楽でもいいんですが、アートでは従来では悪いと思われてしまうようなことも、転覆させて喜びに変えることができます。どんな特徴をもった人たちでも、創造する歓びを味わえる社会って良いですよね。

リーガン・リントン
Phamaly Theatre Company 芸術監督
過去の作品を様々な障害のある役者のみをキャスティングして再表現する非営利の劇団ファマリーの芸術監督。車いす使用者としては唯一のアメリカのメジャー劇団を率いて、演劇の分野でインクルージョンを呼びかける主要な人物。