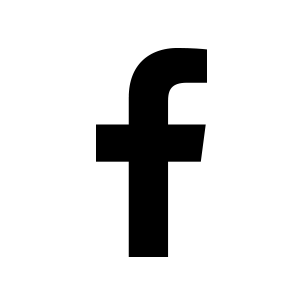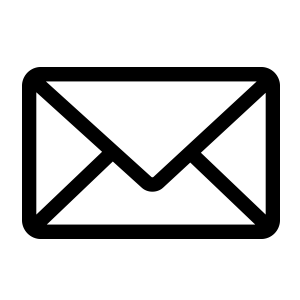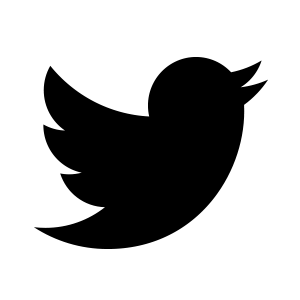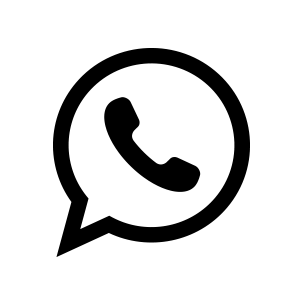voice
アンバサダーの乙武洋匡さん、アドバイザリーパネルの伊敷政英さん、廣川麻子さんとともに、アクセシビリティをテーマに障害当事者としてのそれぞれの視点から見えてくることについてお話いただきました。後半はエンターテイメントの持つ可能性を模索しながら、True Colors Festivalのこれからについて考えます。
視覚障害があってもアイドルにハマるし、聴覚障害があってもライブに行く
乙武:おふたりはご自身も普段からエンタメを楽しむ機会を持っていらっしゃいますか? その場合、どんなところに不便や変化を感じているかを教えてください。

Zoomの画面越しに話す乙武洋匡さんのキャプチャ画像
伊敷:僕は小学校高学年の頃からずっと音楽が好きで、中学校になると「X」にハマり、東京ドームのライブに参加するのが年末の恒例行事になっていました。ただ、すごくいい席が取れたとしても、弱視なのでパフォーマンスが見えません。そこで、自分が行ったライブのビデオを買って、TVに顔を近づけてもう一度見返していました。「あのときのYOSHIKIのソロはこんなパフォーマンスだったんだ」って。
それは大人になってからも同じで、7〜8年前に「ももいろクローバーZ(ももクロ)」にハマったときも一度ライブに行ったのですが、会場では臨場感や歌声を楽しみ、後日映像で視覚的に楽しむという、二段構えの楽しみ方をしました。
乙武:これは単純な好奇心からの質問なんですが……アイドルを推すときって、「可愛い」が大きな要素になるのではないかと思います。見えない場合はどのように判断するのですか?
伊敷:それはすごくいい質問ですね。僕は高城れにちゃん(ももクロのメンバー)を推していたんですが、彼女たちはメンバー一人ひとり色が決まっているんですよ。ほかのアイドルはみんな同じ衣装なので誰がどこにいるのかわからないのですが、「ももクロ」は色分けされているからぱっと見でわかる。当時よく冗談で「「ももクロ」はアクセシブルなアイドルだ」と言ってました(笑)。
また、僕自身は「可愛い」という点はそこまで重視していなくて……ももクロの魅力って、やっぱり全力感にあるんですよ。あれだけ全力で踊られたら、少しくらい見えなくても伝わってくるよね、という。
廣川:声に惹かれるということもあるのですか?
伊敷:好きな声というのはありますね。アイドルや芸能人だけではなく、友人知人にも「この人の声いいなぁ」というのは感じます。
廣川:なるほど。聞こえない人の場合は逆に、見て判断することが多いんです。ダンスがメリハリよくかっこいいとか、表情が魅力的とか。見えない人と聞こえない人で注目するポイントが違うのは面白いですね。
乙武:聴覚障害の方にとってダンスやバレエは鑑賞しやすいのではと想像するのですが、最近は音楽ライブを楽しみにされる聴覚障害者の方も増えていると聞きます。廣川さんもライブに行くことはありますか?
廣川:私自身はあまり音楽ライブに行くことはないのですが、若い聞こえない人たちはジャニーズのライブに行くと聞きます。友達にMCを手話通訳してもらったりして楽しむそうです。歌の間は歌詞が字幕で出ることもあるようですね。
去年(2020年末)、「嵐」の解散ライブ配信に字幕がつくと聞いて、私も初めてジャニーズのライブに参加してみました。ライブではメンバーのキャラクターが伝わってきて楽しかったです。
乙武:私はバリアフリーのコンサル会社の顧問をしているのですが、先日大手芸能事務所から「所属アーティストのファンに聴覚障害のある方がいるのですが、どのようなサポートをするといいでしょうか」と相談を受けました。歌声は聞こえなくても、盛り上がりの中に自分も身を置くという体験を求めて参加されるそうですね。そういうことがあると知らなかったので驚きました。
僕たちはついつい「聴覚障害のある方はライブに来ないだろう」という前提で物事を考えがちですが、想像力を広く持って、参加したいと思ってくれた方に少しでも満足度高く帰っていただくためには何をしたらいいのかを考えなければ、と思いました。

True Colors MUSICALの客席には車椅子ユーザーや視覚障害者の姿もあった(撮影:西野正将)
乙武:車椅子ユーザーとしての視点もお伝えすると、主にふたつの課題があると考えています。ある程度の規模の会場には車椅子席が用意され、物理的なバリアの問題は解消されつつあります。ただ、座席の選択肢が少ないんです。映画館の場合は最前列しかないことが多く、首が攣りそうになりながら鑑賞しなければいけません。
もうひとつは、劇場やスポーツスタジアムに行くと、車椅子席がひとかたまりになっていること。通常の席が周りにないんですね。健常者の友人と一緒に行くと、介助という形で真後ろに配置されたパイプ椅子に座らされたりします。そうすると一緒に観ている感が感じられませんし、友人が居心地の悪い思いをしていないか心配になります。
ヨーロッパはそこが工夫されていて、車椅子席の隣には折りたたみ式の座席が用意されています。車椅子同士であれば折りたたみ、健常者は広げて座ることができる。「誰と行くか」を選ばずに済む設計になっているんです。エンタメを楽しむときは、何を観るかだけでなく、誰と行くかも大事ですよね。とても良い工夫だなと思いました。
「TRUE COLORS」という言葉は、ひとりの人間の中にさまざまな色があることも表している
乙武:ダイバーシティやインクルージョンを推進していく上で、エンタメに期待することはありますか?
伊敷:一緒に楽しむというのが大事なポイントかなと思っています。これまでのバリアフリー上映会や、福祉的な意味合いの強いサポートつきのエンタメとは異なり、多様な人が同じ場に集まってひとつのものを楽しむことができる。楽しみ方が色々あって自由に選択できる。そういう状況が生まれると素敵だなと思います。こうした一緒に楽しむための環境を整えているという点で、True Colors Festivalには大きな可能性を感じています。
廣川:いま伊敷さんがおっしゃったように、障害者のためのイベントではなく、一般の人も楽しめるイベントに多様な人が参加できること。その環境をつくることが求められているし、大事なことなのだと思います。
乙武:僕も同感です。昨年、『ヒゲとナプキン』(小学館)という小説を出版しました。この小説を書いたのは、トランスジェンダーの当事者で活動家でもある友人の杉山文野から、「長年の活動を通して、もともと関心を持ってくれていた人には正しいメッセージを届けることができた。でも、もう一段階遠くの人に届けるには、エンタメの力が必要だ」と頼まれたのがきっかけです。
私は2007年から2010年にかけて小学校の教員を務めさせていただいて、その経験を小説『だいじょうぶ3組』(講談社)という形で発表しました。それが映画化されて、国分太一さんや榮倉奈々さんが出演してくださったんです。すると、障害者や教育の問題にそれまで関心がなかった方も、俳優さんが見たいからと劇場に足を運んでくださった。より広い範囲の方に届けることができたんですね。これがエンタメの力なんだと思います。
障害者のためのイベントではなく、誰が観ても楽しいと思えるもの。問題に関心がなくても観に行きたいと思わせるもの。そういったエンタメ作品を提供していくことが必要なのでしょうね。
乙武:話をTrue Colors Festivalに移すと、おふたりはこれまでどのような関わり方をしてきたのでしょうか。
伊敷:僕は最寄り駅から公演会場までのルート案内をつくりました。よくアクセスのページにGoogle Mapだけ貼り付けているサイトがありますが、それだと視覚障害者単独ではたどり着くのが難しいんです。スタッフのみなさんと実際に会場までの道を歩き、文章と写真で紹介しました。また、ウェブサイトのアクセシビリティに関するお手伝いもしています。

池袋駅地下コンコースにて、イベント会場までの視覚障害者のための最適ルートを検証する伊敷さん(画面左)
廣川:私もさまざまなイベントに参加して、聴覚障害者の立場から改善点を提案してきました。たとえば、『True Colors FASHION』の落合陽一さんの対談配信では、ろう者の手話通訳を起用し、同時に字幕も付与するという試みをさせていただきました。ろう者が自分の言葉で情報を伝えることで、内容もしっかりと伝わったのではないかと考えています。ほかの場でもこうした試みを増やしていけたらと思っています。
一方で、これまではこうしたさまざまな配慮がある情報の発信は少し不足していたのではないかと考えています。情報が足りていないために、「聞こえない人には関係ないイベントだ」と思われてしまうのはもったいないことです。ウェブサイトや動画などを活用しながら、わかりやすく発信していくことが今後の課題だと捉えています。
乙武:ありがとうございます。私はTrue Colors Festivalの取り組みをより多くの人に伝えるためには、「TRUE COLORS」という言葉の意味をもう一度紐解き、わかりやすく伝えることが必要ではないかと考えています。おふたりは「TRUE COLORS」という言葉をどう受け止めていらっしゃいますか?
廣川:直訳すると「真実の色」となりますが、自分に合った色をありのままに表せているかどうか、表した自分を周囲の人が受け止めているかどうか、ということではないでしょうか。それらを大切にしたいというメッセージが込められているのかなと感じています。
伊敷:多様な人がTrue Colors Festivalに参加すること、関わることのイメージとして「TRUE COLORS」という言葉を使っているのかなと感じていました。ただそれは、単にいろんな色を持った人たちが集まる、というだけではありません。たとえば僕が常に青かというとそうではなく、日によって赤になったり黄色になったりする。ひとりの人間のなかに、いろんな色があっていいはずです。「TRUE COLORS」と複数形になっているのは、そういう意味が込められているのかなと思っています。
乙武:とても同感です。「日によって自分の色も違うよね」というところまで踏み込まないと、「この障害のある人ってこの色だよね」とカテゴリーごとに色をつけられて、新たな息苦しさを生んでしまうかもしれません。一応自分はこのカテゴリーに分けられるかもしれないけど、そうとも言えない自分もいる。そうした曖昧さを許容してくれる社会が良いですね。
物理的なアクセシビリティが整備されると、自然と精神的・感覚的なアクセシビリティも改善されていくのかもしれない
乙武:編集スタッフのみなさんからも何か質問はありますか?
スタッフ:True Colors Festivalでは車椅子席を準備したり、音声ガイドや舞台手話通訳を手配したり、より多くの人に鑑賞体験を提供できるよう環境づくりを進めていますが、そこで実現される多様性は一時的なものにすぎません。どうすればダイバーシティ&インクルージョンへの意識を日常に浸透させていくことができるでしょうか?
伊敷:最初に乙武さんがおっしゃった差別と偏見の話に近いかもしれませんね。精神的な部分・感覚的な部分を変えることは難しいし、そもそもそこまで踏み込んでいいのかという疑問も生じます。時間をかけて、少しずつ自然に変わっていくものなのかなと思います。
実際、20年前といまとで意識は変わってきています。20年前は、エレベーターに乗り込む際、中の人に「これは上に行きますか、下に行きますか」と聞いても誰も答えてくれず、ドアが閉まってしまうことが普通にありました。いまはほぼ100%答えてくれますし、「何階に行きますか」とボタンを押してくれます。まずは物理的なアクセシビリティを改善する取り組みを続けることで、じわじわと水が染み込むように広がっていくのかな、と感じています。
廣川:伊敷さんに同感です。偏見や差別は、知らないから起こるという側面が大きいと思います。会って話すことでわかることも多いので、そういう場を増やすことが大事なのではないでしょうか。
昔はお店で店員さんに話しかけられたときに、「私聞こえない」というジェスチャーをすると、何も言わず逃げて行ってしまったり、ずっと変な目で見られていたり、繰り返し声のみで話しかけてきたり、といったことがありました。いまは、ジェスチャーや筆談で伝えてくださる方が本当に増えたと実感しています。聴覚障害者のことが知られてきているんですね。啓発の大事さを感じています。
乙武:僕は普段、情報系の番組に出るときは長袖のスーツを着るようにしているのですが、先日番組後半で食事をする場面があったので、食べやすいように半袖を着て、さらに袖を折り返した状態で出演したんです。つまり、腕が丸見えの状態だったんですね。そうしたら、ネットで「なんで長袖着ないんだ」「腕を隠しておけ」という書き込みが散見されまして。
感覚的に「気持ち悪い」と思われることまでは、ある程度仕方ないことだと思うんです。なぜかというと、最近研究者の方から聞いたのですが、AIが犬の画像を見て「これは犬だ」と判断できるようになるためには、何百万という数の犬の画像を読み込ませる必要があるそうです。人間の脳も同じ構造をしていて、手足のある姿をたくさん見て「こういうものが人間だ」と判断している。そう考えると、手足のない人間のデータを読み込んだことがない人が、僕のように珍しい身体の人間を見てぎょっとしてしまうのは本質的な反応なんだな、と納得できます。でも、本人に聞こえるように「気持ち悪い」と言ったり、ましてやネットに書き込むなんていうのは考えものです(笑)。
大事なのは、そうした言葉を投げつけられない環境であることが保証されていることではないでしょうか。
廣川:お話を聞いていて、見慣れているかどうかは手話通訳にも共通することだなと思いました。コロナ以降、ニュースなどさまざまなものに手話通訳がつくようになり、多くの人が手話通訳を見慣れてきているように感じます。手話通訳がないものに対して「なぜないんだろう?」と思うようにすらなってきたのではないでしょうか。見慣れてもらうために、積極的に出していくことが必要なのでしょうね。

True Colors DIALOGUEには、TA-net舞台手話通訳チームから加藤裕子さん、水野里香さん、フリーランス通訳者の橋本一郎さんが出演した。画像左端に座っている3名。(撮影:冨田了平)
乙武:本当に、「慣れる」というのは大事なことだと思います。私は今日、伊敷さんのお話を聞くときは声に出して相槌を打ち、廣川さんのお話を聞くときは声には出さず頷く仕草や表情で伝えるようにしていました。事前にそうしようと考えていたのではなく、途中でそうしたほうがいいだろうと気づいて調整したのです。これはおふたりと話すという経験を経て気づいたことですが、次にこういう機会があれば最初から意識することができるかもしれません。慣れるための機会があることが大事なのでしょうね。
伊敷:たしかに、乙武さんすごく反応を声に出してくれるなと感じていました。さすがですね。話しやすかったです。
地方におけるアクセシビリティを考えながら、True Colors Festivalを進めていく
乙武:最後に、おふたりがTrue Colors Festivalの今後に期待することを教えていただけますか?
廣川:コロナ下で集まる機会が無くなり、オンライン配信という新しい形が生まれるなどいいこともあったものの、やはり集まることの良さというものがありますよね。True Colors Festivalでは今後、全国色々なところを周る取り組みも始まると聞いています。現場で触れ合うことの楽しさを味わいながら、可能性を広げていただきたいと思います。
また、東京や大阪と比べると、地方はまだまだアクセシビリティや環境が整っていない面もあるのではないでしょうか。地方の方々の気づきが生まれる場をつくっていただきたいと期待しています。
伊敷:廣川さんがおっしゃったとおり、都市部と地方では、障害のある人の生活状況は大きく異なりますよね。東京は公共交通機関と徒歩で公演会場にアクセスできますが、車社会の地方では、誰かの助けを借りなければ外に出ることすらできない視覚障害者もいらっしゃるのではないかと思います。これまでの公演でやってきたように最寄り駅からのルート案内をそのまま載せればいいということではないはずです。地域によって求められることは違うと思うので、一つひとつ丁寧にアクセシビリティを考えていきたいですね。
また、先ほどの話につながりますが、「障害者のためのイベント」ではなく「普通のイベント」にしていくために、クオリティを妥協してほしくないなと思います。たとえばコンサートを行うときに、「障害のあるアーティストだから」とオーディションの基準が下がってしまったら、観に来た視覚障害者は「下手だな」とすぐにわかるしがっかりしてしまう。高いクオリティの作品を提供しつづけてほしいです。
乙武:私からもひとつだけ要望をお伝えするなら、読後感の爽やかな小説のようにしてほしくないな、と思っています。いいことをやろうとするとどうしても道徳的になりがちですが、そうするとあまり心に残らないものになってしまう。
むしろ、引っかかりやモヤモヤを残すことに意義があるのではないでしょうか。鑑賞直後は納得がいかなかったり、違和感を抱いたりして、その後の生活のなかで、「あ、これはあのときに観たものとつながっている話じゃないか」とか、「あれってこういうことだったのか」と気づく。そうした引っかかりや、ざらっとした感触が残るイベントになったらいいな、と期待しています。
鼎談の前半はこちら
(インタビュアー:安藤寛志、平原礼奈、森下ひろき テキスト:飛田恵美子)
乙武洋匡
True Colors Festivalアンバサダー
1976年、東京都出身。先天性四肢欠損により、幼少時より電動車椅子にて生活。大学在学中に著した『五体不満足』が600万部を超すベストセラーに。海外でも翻訳される。大学卒業後はスポーツライターとして活躍した後、小学校教師として教育活動に尽力する。ニュース番組でMCを務めるなど、日本のダイバーシティ分野におけるオピニオンリーダーとして活動している。
伊敷政英
True Colors Festivalアドバイザリーパネル
Cocktailz代表、アクセシビリティコンサルタント、視覚障害当事者
1977年東京生まれ。先天性の視覚障害で、ロービジョンと全盲を行ったり来たり。今は全盲より。2001年頃よりウェブアクセシビリティに関心を持ち、2003年よりコンサルタントとして企業や自治体・省庁などのウェブサイトにおけるアクセシビリティ改善業務に従事。2010年8月、個人事業としてCocktailzでの活動をスタート。ウェブアクセシビリティ分野での仕事を継続しつつ、ロービジョンの子供にも使いやすくてかわいい・かっこいいノート「KIMINOTE(きみのて)」の企画・制作を行っている。
廣川麻子
True Colors Festivalアドバイザリーパネル
NPOTA-net理事長、東京大学先端科学技術研究センター熊谷研究室、聴覚障害当事者 2012年に観劇支援団体の特定非営利活動法人シアター・アクセシビリティ・ネットワーク(TA-net)設立。平成27年度芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞。2018年より東京大学先端科学技術研究センター当事者研究分野ユーザーリサーチャーとして観劇支援の研究に取り組む。NHK「手話で楽しむみんなのテレビ」2019年の立ち上げ時から監修を担当。