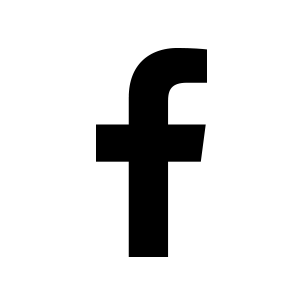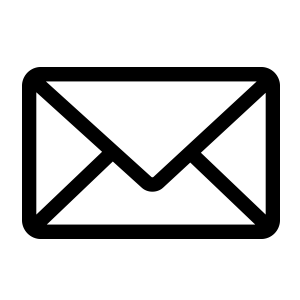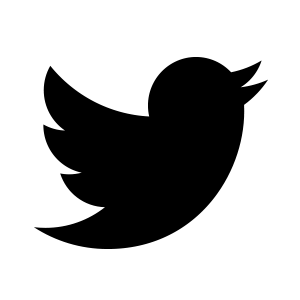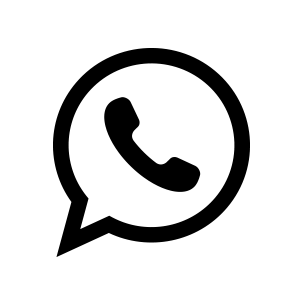voice
2021年の東京はオリパラ開催をきっかけに、駅などのバリアフリー化が進んだように感じます。今回はアンバサダーの乙武洋匡さん、アドバイザリーパネルの伊敷政英さん、廣川麻子さんとともに、ダイバーシティ&インクルージョンの現在や、エンターテイメントの楽しみ方や課題について、それぞれの視点からお話いただきました。たくさんの学びと気づきのあった鼎談の様子を、2回にわけてお届けします。
「ダイバーシティ」と「インクルージョン」。その言葉が表すものとは?
乙武:まずは伊敷さんと廣川さんから、障害の特性や普段の活動を紹介していただけますか?
伊敷:伊敷政英といいます。先天性の視覚障害があるのですが、2〜3年前までは弱視でした。(2021年)10月から12月まで放映されていたドラマ『恋です!〜ヤンキー君と白杖ガール〜』(日本テレビ系列)に出てくる主人公のユキコちゃんとおそらく同じくらいだと思うのですが、0.01ほどの視力があって文字を読んだり書いたりすることもできました。ただ、この2年ほどで急激に視力が落ちてしまい、現在はほぼ全盲の状態です。
普段の活動についてですが、企業やNPO、自治体のwebアクセシビリティ改善のコンサルティングをしています。
Zoomの画面越に話す伊敷政英さんのキャプチャ画像 廣川:廣川麻子と申します。最初に、私のサインネームを紹介します。聞こえない人たちは、手の形でその人の特徴を表現し、あだ名のように使うんです。まず手を握って親指だけ出し、横に倒します。「あ」を表す指文字ですね。そのとき、手のひらは相手のほうに向けます。その手を口元に持っていき、親指をえくぼのあたりにつけて手首を何度か捻ります。これが私のサインネームです。 乙武:すごい、伊敷さんは見えていないのに完璧にできていましたね。 伊敷:はい(笑)。廣川さんの説明が的確でわかりやすかったからです。 自身のサインネームを紹介する廣川麻子さん 廣川:大学生のときから、見えない学生、聞こえない学生、車椅子の学生などが一緒に活動する機会があって、一緒に遊ぶために必要な工夫を積み重ねてきました。それが今の活動にもつながっていて、演劇や文化芸術を一緒に観て楽しむためには何が必要なのか、常日頃考えています。具体的には、『シアター・アクセシビリティ・ネットワーク(TA-net)』というNPO法人を立ち上げ、見えない人、聞こえない人が楽しく観劇できるよう、字幕、手話通訳、音声ガイドなどをつける活動をしています。 乙武:ありがとうございます。私も自己紹介をしますと、先天性四肢欠損という手足がほとんどない状態で生まれてきました。身体障害者ということになりますが、これまで交流があったのは車椅子ユーザーが主で、聴覚や視覚に特性のある方がどんな不便や困難を感じているのか深く突っ込んで聞く機会はあまりなかったんです。だから、今日おふたりと話せることを楽しみにしていました。よろしくお願いいたします。 さて、さっそくひとつめのテーマに入りたいのですが、この数年でダイバーシティ&インクルージョンという言葉がよく使われるようになったと思います。日本語にすると多様性と包摂。並んで使用されることが多いため同じ意味を持っているように捉えられる傾向がありますが、私は少し意味合いが異なる言葉なのではないかと考えています。 似た例として、差別と偏見があります。よく「差別と偏見をなくそう」と一緒に語られますが、偏見とは「こういうカテゴリーの人はこういう傾向にあるよね」といった風に、特定の見方をすること。いわば心の中の問題です。一方差別は、そうした偏見に基づいて、合理性なく特定の人々に低い扱いをすること。心の中を飛び出て、言動に移すことですね。 社会から排除されてしまう、商品やサービスを受け取れなくなってしまう差別は絶対になくしていかなければいけません。でも、偏見まで無くすのは難しいのではないかと思いますし、人の心の中のことにまで踏み入っていいのだろうかという疑問も浮かびます。並列に語られがちですが、本来は別々に考えなければいけない事柄なのだと思います。 同じことがダイバーシティ&インクルージョンにも言えるのではないか……というのが私の考えなのですが、おふたりはダイバーシティとインクルージョンをどう捉えていらっしゃいますか? 伊敷:正直なところ、ダイバーシティもインクルージョンも英単語としての意味は理解しているものの、それがいまの社会の文脈でどのように定義づけられどのような活動につながっているのか、あまり具体的なイメージは持っていませんでした。勝手な印象で言うと、ダイバーシティは障害のある人の話だけではなく外国人や小さなお子さんのいる家庭など幅広い層を扱う考え方で、インクルーシブの方は障害のある子どもと健常者が一緒に学ぶインクルーシブ教育などの例から、より障害のある人をターゲットにした言葉なのかな、と捉えています。 廣川:ダイバーシティはそれぞれがありのままであるということだと思います。たとえば私のように生まれたときから耳が聞こえない人は、聞こえる人に合わせるため半ば強制的に発声訓練を受けさせられてきました。本来ならば、聞こえなければ聞こえない人の言語である手話を使う。手話の後に日本語を覚えて、書く力読む力を身につける。その上で、音声で話したい人は発声訓練を受けるというのが適切な形だと考えています。 聞こえない人によっても考え方はそれぞれ異なります。声で話したくない人に対して「聞こえる人に合わせて話せるようになりなさい」と押し付けるのも、話したい人に対して「聞こえないのに声を出すのはおかしい」と否定するのも、どちらも良いことではありません。そうではなく、本人の意志を尊重するのがダイバーシティではないでしょうか。 *手話の歴史や位置付けなどについてもっと詳しく知りたい方はこちらへ 知られざる手話の世界(編集部) インクルージョンは、そうしたありのままで参加できる環境をつくることだと捉えています。たとえばこの場にも、手話通訳の方が2人参加してくださっていて、1人は私が手話で話したことを声でみなさんに伝え、1人はみなさんが声で話したことを手話で私に伝えてくださっています。手話通訳をつけることを聴覚障害のある私から依頼するのではなく、企画する側が最初から環境を整えてくださる。その上で足りないことがあれば相談できる。そんな環境です。 岡田直樹さん(画面中段左手)と田村梢さん(中段右手)による手話通訳。岡田さんは口語を手話で、田村さんは手話を口語で伝える役割を担当 乙武:さきほど私が偏見と差別を例に出したのは、ダイバーシティとインクルージョンがそれに対応する言葉なのではないかと思っているからなんです。ダイバーシティ、多様性は「色んな人がいていいよね、違いがあっていいよね」という考えで、偏見の真逆。インクルージョン、包摂は差別の反対で、違いのある人が社会に参加できるようにする、商品やサービスを受けられるようにすること。 そう考えたとき、この数年で多様性は進んだと思います。一方で、包摂はどこまで進んだのだろうかということが気になっています。おふたりの感触を教えていただけますか? 廣川:文化芸術に関して言うと、私がNPOを始めた8年近く前と比べると、字幕や手話通訳がつく機会が増えていると感じます。昔はゼロでした。台本を借りることも一苦労だったんです。聞こえない人には台本の貸し出しが必要なんだという理解が広まり、一般的なサポートとして行われるようになりました。字幕をつける予算も取りやすくなっている状況です。 その背景には、文化芸術に関する法律が改正され、情報保障のためのサポートが必要だと明記されたことも大きく影響しています(障害者文化芸術活動推進法、2018年6月施行)。全体の劇場数からいうとまだわずかですが、公立の劇場をはじめとして、少しずつサポートのつく劇場が増えてきているのは喜ばしいことだと考えています。 ただ、“芸能人”が出演するような商業演劇や大きなミュージカル等、企業が主催する公演にはまだあまりサポートがついていない状態です。台本の貸し出しがやっと始まったくらいですね。また、著作権の問題から歌詞は台本に記載されません。歌が始まると、聞こえない人は歌詞がわからないまま鑑賞しなければならないんです。こうした細かな問題はまだまだ残っています。 乙武:サポートが増えたのは、当事者によるロビー活動が実った結果なのでしょうか、それとも時代の流れにより自然と環境が整っていたのでしょうか。 廣川:両方ですね。障害者差別解消法(2016年4月施行)、さらに障害者芸術文化推進法(2018年6月施行)が制定され、社会的にこれは差別なのではないかという見方が出てきたこと、オリパラの開催に伴い改善していこうという機運が高まったこともあったと思います。 伊敷:視覚障害のある僕の肌感覚では、ICT(情報通信技術)の進歩・普及と、視覚障害者の生活のしやすさは比例して良くなっているように感じています。インターネットが普及する前は、情報を得ようとすると誰かに読んでもらったり点字にしてもらったりと人の手が必要でした。マンパワーも不足していたし、情報の取得にタイムラグがある、プライバシーを守れないという問題もありました。 いまはあらゆる情報がウェブサイトに掲載されているので、画面拡大ソフトやスクリーンリーダーを使い自分で情報を入手することができます。必要なときに、好きなだけ繰り返して情報を得られる。本当に画期的なことで、インターネットのおかげで生活ががらりと変わりました。 あとはやっぱり、スマートフォン・タブレット端末の登場ですね。「iPhone(アイフォーン)」や「ipad(アイパッド)」にはアクセシビリティを当たり前に実装しようという強い意志を感じました。早い段階からボイスオーバーという音声読み上げ機能が搭載されていたし、特別なアプリを使わなくても文字をズームしたり色を反転したりできた。最初はつるつるのタッチパネルを見て、「俺たち使えないじゃん」と思ったんですが、その点もしっかり考慮されていて、いざ手にしてみるとすごく便利だったんです。 amazonの「Kindle(キンドル)」があれば本を読めるし、ナビアプリを使えば自分ひとりでも目的地にたどり着けるかもしれない。そういう情報が新しいもの好きの視覚障害者からメーリングリストやSNSを通して発信されて、どんどん可能性が広がっていきました。 エンタメ分野で大きかったのは、「UDCast(ユーディキャスト)」の登場です。視覚障害者が映画を観るときは音声による解説が必要です。以前はボランティアが配給会社から台本を借りて、状況や俳優の仕草、表情を説明する音声ガイド専用の台本を書き、映写室に入れてもらってFMラジオを使って情報を伝えるということをしていました。この方法によって、バリアフリー上映会を開くことで映画を観ることができるようになりました。さらに「UDCast」が登場したことで、いつ劇場に行っても音声解説つきの映画を観ることができるようになり、より選択肢が広がりました。アクセシビリティ改善のすばらしい例だと思っています。 字幕や手話の表示、音声ガイド再生等を行うことのできる無料アプリケーション「UDCast」 乙武:ICTによるインクルージョンの進歩は、車椅子ユーザーとしても大いに感じています。一例を挙げると、オリィ研究所という会社が「OriHime(オリヒメ)」という遠隔操作ロボットを開発しているのですが、重度の障害がある方や難病の方に働く喜びを提供するため、2021年6月にはこのロボットを通じて働けるカフェを日本橋にオープンしました。家から出ることができない方でも接客業ができるようになったんです。すごく可能性が広がったなと思います。 廣川さんも、ICTの発展によるインクルージョンの進歩は感じていらっしゃいますか? True Colors FASHION撮影現場(2021年6月)より、東芝の「koestation(コエステーション)の技術と、オリィ研究所が開発した視線入力技術を組み合わせた「ALS SAVE VOICE PROJECT(ALS セイブボイスプロジェクト)」を使い、声を失ったあとも自身の声でコミュニケーションを続ける、武藤将胤さん(撮影:冨田了平) 廣川:はい、かなりの恩恵がありました。たとえば、音声を文字に変換してくれるUDトークというアプリが登場しました。イベントなどの際にリアルタイムで字幕を付与することもできます。まだ言葉が正確に認識されないこともあり修正が必要ですが、以前と比べるとすごく便利になったと思います。 ネットが普及したことで、今回のような遠隔手話通訳や、遠隔での字幕付与もできるようになりました。また、コロナ下で情報保障の面はかなり前進したように感じています。Zoomのようなツールは以前からありましたが、この2年でみんなが使うようになり、機能も向上しましたし、多くの人が操作にも慣れてきました。 情報発信の面でも向上が見られます。良い例があるのでご紹介しますと、今度ライブをされる方から、手話通訳をつけたいとご相談を受けたんです。なぜ手話通訳をつけたいと思ったのか聞くと、「ネットで海外のライブを観たら、ライブの状況をかっこよく手話通訳していて、日本でもやりたいと思った。ぜひ聞こえない人にもライブを観てもらいたい」とのことでした。以前は福祉的な意味合いでご相談いただくことが多かったけれど、最近は「一緒に楽しみたい」という視点から考えてくださる方が増えてきているのかな、と感じています。 True Colors DANCEでは、イベントの司会を字幕と手話通訳で伝えた(撮影:冨田了平) 乙武:車椅子ユーザーもコロナにより大きな影響を受けました。我々が労働市場に出るときに大きな壁となっていたのが通勤です。車椅子のまま満員電車に乗り込み目的地までたどり着くのは至難の技で、これを月曜から金曜まで行うのは厳しいものがありました。これまでもフレックス通勤などの制度を整えている会社はありましたが、コロナ下で「障害者のため」ではなく、「感染拡大を防止するため」「労働者全体に」リモートワークが推進され、社会全体の価値観が変わりました。通勤に難を抱えていた交通弱者にとっては、力を発揮しやすい環境になったのではないでしょうか。 鼎談は後半に続きます。 乙武洋匡 伊敷政英 廣川麻子


ICTの進化がインクルージョンを後押しした



(インタビュアー:安藤寛志、平原礼奈、森下ひろき テキスト:飛田恵美子)
True Colors Festivalアンバサダー
1976年、東京都出身。先天性四肢欠損により、幼少時より電動車椅子にて生活。大学在学中に著した『五体不満足』が600万部を超すベストセラーに。海外でも翻訳される。大学卒業後はスポーツライターとして活躍した後、小学校教師として教育活動に尽力する。ニュース番組でMCを務めるなど、日本のダイバーシティ分野におけるオピニオンリーダーとして活動している。
True Colors Festivalアドバイザリーパネル
Cocktailz代表、アクセシビリティコンサルタント、視覚障害当事者
1977年東京生まれ。先天性の視覚障害で、ロービジョンと全盲を行ったり来たり。今は全盲より。2001年頃よりウェブアクセシビリティに関心を持ち、2003年よりコンサルタントとして企業や自治体・省庁などのウェブサイトにおけるアクセシビリティ改善業務に従事。2010年8月、個人事業としてCocktailzでの活動をスタート。ウェブアクセシビリティ分野での仕事を継続しつつ、ロービジョンの子供にも使いやすくてかわいい・かっこいいノート「KIMINOTE(きみのて)」の企画・制作を行っている。
True Colors Festivalアドバイザリーパネル
NPOTA-net理事長、東京大学先端科学技術研究センター熊谷研究室、聴覚障害当事者 2012年に観劇支援団体の特定非営利活動法人シアター・アクセシビリティ・ネットワーク(TA-net)設立。平成27年度芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞。2018年より東京大学先端科学技術研究センター当事者研究分野ユーザーリサーチャーとして観劇支援の研究に取り組む。NHK「手話で楽しむみんなのテレビ」2019年の立ち上げ時から監修を担当。