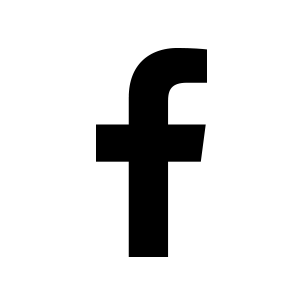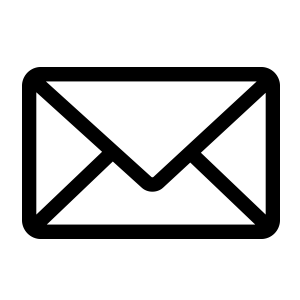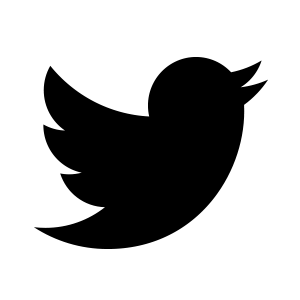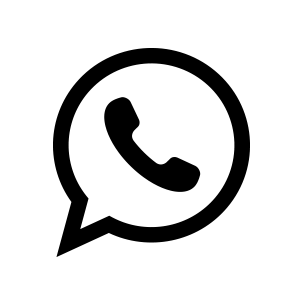voice
【Meet The Family(TCFファミリーの素顔)】True Colors FASHIONから、島影圭佑さんに、ファッションショーで濵ノ上文哉さんが身につけたメガネ「OTON GLASS」開発までの経緯や、思い描く未来についてお聞きしました。
True Colors FASHION:身体の多様性を未来に放つダイバーシティ・ファッションショー
Q: OTON GLASSや現在取り組まれているFabBiotopeの活動内容について教えていただけますか?
はい、まずFabBiotopeは方法論を中心とした知の流通によって自立共生する弱視者やエンジニアを増やすプロジェクトです。父の失読症をきっかけに、文字を代わりに読み上げるメガネOTON GLASSを仲間と共に発明し、そこから発展する形で生まれたのがFabBiotopeになっています。ここではプロジェクトの参加者である弱視者とエンジニアを「当事者兼つくり手」として同じ水平面上に立つ者として招きます。それによって福祉における依存の問題、情報技術における格差の問題にアプローチし、その先に今まで存在することが難しかった個別性や多様性がありのまま存在する社会を夢想しています。

21_21 DESIGN SIGHTで開催された「トランスレーションズ展 −『わかりあえなさ』をわかりあおう」でプロジェクトを紹介している様子
具体的には、独自の工夫によって自らの生き方をつくっている弱視者と協働し、似た課題感を持つ弱視者に向けて、書籍やワークショップの形で当人の方法論を中心とした知を流通させる。同じくエンジニアの場合も、主にメディアアーティストや情報工学研究者と協働し、当事者として情報技術を造形する型を流通させる。またこれら実践の過程で紡がれた関係性を元に、弱視者とエンジニアで協働して発明を実践し、同様にそこで生まれた知を流通させていく活動への発展を企図しています。
そしてこの活動によって生まれる共同体自体を、新たな個別性や多様性を存在させる社会であるとし、そのオルタナティブな社会を造形することに取り組み続けているのが本プロジェクトです。
多様性の問題は言うまでもなく複雑な社会課題です。であるからこそ超個人的に取り組む必要がある。情報技術の民主化を前提に今一度その目的を問い直したい。創造的な弱視者やエンジニアの個別のからだのふるまいをひとつの答えとし、デザインリサーチの技巧によって書籍などに編集し流通させる。メディアによって人間像自体が定義されることを前提に、新旧のメディアを横断しそれを個人が取り戻す試行錯誤、本プロジェクトにおいてはそういった実践性を重視して活動しています。
Q: OTON GLASSとのコラボレーションによって「beta post」から二重に像が重なり合うプリントデザインのリバーシブルコートが誕生しました。このコラボレーションは、島影さんにとってどのような体験でしたか?
「beta post」のデザイナーである江崎賢さんとの出会いが刺激的でした。私も身近な人でファッションデザインに関わっている方はいるんですが、新興性が高かったり学術性が高かったりと、共通の言語としてデザインリサーチみたいなものがあって交流できている人がほとんどで、いわゆる自分のブランドを持ってファッションのシステムの中で活動されているデザイナーの方となにか一緒にやるというのは実質初めての経験でした。なので、そもそものコミュニケーションの手かがりみたいなものがあるのか、出会う前は少し不安な気持ちでした。
しかし、実際にお話して、また今までの作品などを見させてもらって、思想部分で共鳴するところが大いにあると感じて、それ以降は私自身が気になることを江崎さんに質問しまくって「beta post」研究、江崎さん研究を進めるような形となりました(笑)。具体的には、あくまで私個人の感覚なのですが、まず江崎さんは、我々現代人の「消費」に偏重しきっていることによって生まれる無意識の認識や行動にアプローチされている。またその際に江崎さん自身が身の回りにある人工物の見立てを転がしながら、服やアイテムのアイディアを発想しつつ、またその実践者として決まった住居を持たない人々の工夫、野生の創造性を参照している。
このスタイルは、もちろん扱ってるメディウムや技法は違うものの、私自身のやりたいことと根本的な部分で繋がっていると感じました。まず私にとっては分野は違うんだけれど、そういう根本的な部分で共鳴できる人がいる、その出会い自体がものすごく衝撃的な出来事でした。
あとは純粋に江崎さんの自分自身が思考していることが服やアイテムとして物質化するときの精度だったり、流通するビジュアルなイメージ、言葉、場に対して彼の美学をベースにした清々しい編集指針だったり、そういった部分にも感銘を受けていました。
私自身、なにかを形にするのに時間がかかるタイプの人間なので、今回はただただ楽しく参加させていただいてしまった感覚なのですが、今回設けていただいた出会いの機会をきっかけに「beta post」さんと今後新たな協働の制作に発展できればと個人的に願っています。具体的に、私自身あまり詳しいわけではないのですが、戦後の洋裁文化を参照して、今回の取り組みを実験的な「実践」と位置付けるなら、そこで生まれた型紙や方法論といった知を書籍やワークショップの形で流通させたり伝授したりすることができればと勝手に考えています。今、私自身は弱視の方やエンジニアの方とそれを実践しているという感覚なのですが、私自身のその型が洗練されていったタイミングで再び「beta post」の門を叩ければ…と思っています。それまで私自身精進して、なんとか生き延びて、また出会い直せればと願っています。

OTON GLASSとbeta postによるジャケットをまとい、白杖を手にランウェイを歩く濵ノ上文哉さん(撮影:冨田了平)
Q: ショーへの参加をきっかけに様々な身体・ファッション・テクノロジーを持って活動する方々と出合い、感じたこと、考えたことなどありましたら教えてください。
とにかく総合演出の落合さん、プロデューサーの金森さんが手を取り合うことで、このような場が立ち上がるんだと、まさに新たな祝祭が立ち上がる瞬間を目の当たりにできたという感覚で、感動しっぱなしでした。
コロナ禍だったり短期間のスケジュールだったりの制限の中で、ファッションショーが実現できたのは、もちろん現場の様々な人の努力があると思うのですが、やはり落合さんと金森さんのお二人が出会う以前のそれぞれの実践があって、その積み重ねを前提に、ショーとして爆発したというか、結実したんだなと見ていて、いや本当に素晴らしいなと、そういう感動の気持ちがからだに充満しているような感覚です。
今回のファッションショー開催の前に、金森さんにお声がけいただいて「True Colors FASHION メガ会議『多様性時代のファッションデザインとは?』というのを企画させてもらいました。その際に登壇者として落合さんにお話をしていただいたんですが、そこで落合さんはイヴァン・イリイチのコンヴィヴィアリティの日本語訳を「祝祭」なのでは?と我々に問いかけます。
私の中でその問いが残り続けて、その後ファッションショーの撮影の現場に入りました。そこには紛れもなく祝祭が立ち上がっていた。「バックヤードの祝祭性」と言えるものが、そこにはありました。モデルである障害当事者もエンジニアもファッションデザイナーも、ファッションショーをつくり上げるその構成員として同じ水平面上(舞台と言ってもいいかもしれない)に立っていて、それはある種、その役を演じている状態だと思うんですけれど、その状態が一時的に、仮設的に起きることで、普段の日常の延長線上ではありえない出会い方みたいなのが発生していたように思えます。落合さんの言葉でいう「悦な体験」というのが現場に、バックヤードにあったような気がするのです。なのでコロナ禍における新たな祝祭というのを見せてくれた、体験させてくれたものとして、私にとってこのショーは映っています。
この現場で記録されたものが編集され、同じ時間にそれぞれの場所で同時性を持って観られる。おそらくそこで重要なのは、手段ではなくて画面から悦が染み出ちゃっているかということなんだと思います。まず前提として現場に、バックヤードに祝祭が立ち上がっているか。コロナ前の祝祭と比べると、小さな規模の祝祭なんだけれど、コロナ禍でも可能なサイズで、祝祭の火を消さない。ここで生まれた悦の感覚を、その場にいない人にどうにかこうにかして共有しようとする。そこで新たな工夫としての創造性を生んだり、新たなメディアの造形性を発明していく。それがこれからの祝祭を新たにつくっていく地道なんだけど堅実な実践に思えます。
ファッションショーで、それを実践を通じて実験する。これからの私たちの生活、それを支える祝祭を考える上での大きなヒントを与えてくれる取り組みだったと思います。まずはその経験をさせてもらえたことに、今回のショーの企画・運営をされた皆様に感謝したいです。そしてここでの経験を元に、私自身の活動においてどのように実践するか、また自らの日常をどう新しくつくり直していくか、自身の日々の営みに反映して私なりの答えを探していきたいと思います。

インタビュー収録での、島影さん(画面中央)、総合演出の落合陽一さん(画面右手)、濱ノ上さん(画面左手)が並んで話をしている様子(撮影:冨田了平)
Q: True Colors Festivalは多様性とインクルージョンを称える芸術祭として、特に海外に向けて「One World One Family(世界は一つの家族)」というキーワードでPRを行なっています。島影さんの考える「ワン・ワールド・ワン・ファミリー」について教えてください。
私は自分の考えを整理するために「小さな社会を造形する」という言葉を普段使っています。「One World One Family(世界は一つの家族)」というキーワード、素晴らしいですよね。詩というか、あってほしい世界を表現しているビジョナリーな言葉で、誰かがそれを描く必要があると思うんですけど、True Colors Festivalがそれをしてくれている。だから、今回のショーも含めて様々な方がプロジェクトに参加されて、ひとつの運動のようになっているんだろうなあと感じます。
私の場合は自分で大きな言葉を使ってしまうと、自分の日常から問題が離れてしまう気がしてしまったり、生活者の自分とつくり手の自分が乖離してしまったりする感覚があって、超個人的なことが小さな普遍につながるような言葉や実践を日々模索している感覚があります。
超個人的になにかをつくること、それによって自分自身の少数派性が可視化される。またそこで生まれた知を似た課題感を持った人におすそ分けする。それらによって生まれる繋がり、その中で発生する必然的な協働。その共同体を小さな社会だとして、実はそれは造形できるものなんじゃないかと、そういった希望を持って私は日々活動しています。
その小さな社会がぽつぽつと点在していて、それら自体が関係し合うことを試みる。そのような小さな社会の存在を前提として、それらが関係し合うことを試み続けたその先に、もしかしたらTrue Colors Festivalが描いてるビジョンに、私なりのアプローチで同じように近づいていくということがありえるのかもしれません。
私の実践は個人的なスケールでの取り組みで、明らかな結果が見えてくるのにとても時間がかかってしまうものかもしれないのですが、現状の私なりの仮説を信じて地道に実践を重ねていければ…と思っています。また皆様となにかご一緒できる日を楽しみにしております。
島影圭佑
起業家
父の失読症をきっかけに文字を代わりに読み上げるメガネ〈OTON GLASS〉を仲間と共に発明。自立共生する弱視者やエンジニアを増やすプロジェクト〈FabBiotope〉に取り組む。近著に『FabBiotope1.0→2.0』、『Prototyping with OTON GLASS』(株式会社オトングラス、2021年)がある。