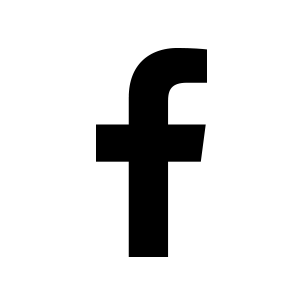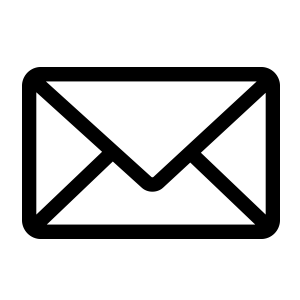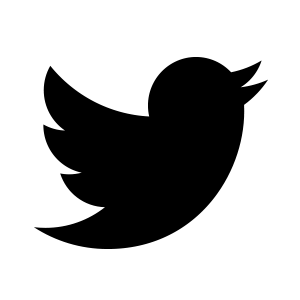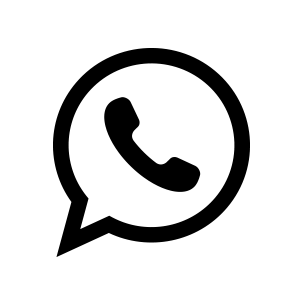voice
2016年にシンガポールで障害のあるアーティストたちの芸術祭「True Colours Festival Singapore」を指揮し、現在はTrue Colors Festivalのエグゼクティブ・プロデューサーを勤めているオードリー。これからのTrue Colors Festivalで伝えていきたい思いや、コンサートまでの道のりについて聞きました。
Q: 渋谷でのダンスイベントを皮切りに、いよいよTrue Colors Festivalがスタートしました。すでに他にもいくつかのプログラムが動き出していますが、今の感想を教えてください。
True Colors Festivalがストリートダンスから始まったのは、非常にいいことだと思っています。日本のストリートカルチャー、なかでもストリートダンスの役割は重要ですし、True Colors DANCEにはワールドクラスのダンサーもたくさんでていました。屋外広場という開かれた場でのイベントは非常にインパクトがありますし、反応もとてもよかった。一方で後に続くTrue Colors BEAT、True Colors JAZZ、True Colors ACADEMYというプログラムは、それぞれ違うコミュニティに向けて発せられています。ジャンルの違うパフォーマンスを特集し、多様なプログラムを順に届けていくことで、人々の交流が促され、カルチャーやジャンルの境界線そのものを破壊していく役割も果たせる。この先にあるコンサートに向けて、コミュニティが次々に繋がっていくいい状態だと思います。
Q: 渋谷でのダンスイベントを皮切りに、いよいよTrue Colors Festivalがスタートしました。すでに他にもいくつかのプログラムが動き出していますが、今の感想を教えてください。
True Colors Festivalがストリートダンスから始まったのは、非常にいいことだと思っています。日本のストリートカルチャー、なかでもストリートダンスの役割は重要ですし、True Colors DANCEにはワールドクラスのダンサーもたくさんでていました。屋外広場という開かれた場でのイベントは非常にインパクトがありますし、反応もとてもよかった。一方で後に続くTrue Colors BEAT、True Colors JAZZ、True Colors ACADEMYというプログラムは、それぞれ違うコミュニティに向けて発せられています。ジャンルの違うパフォーマンスを特集し、多様なプログラムを順に届けていくことで、人々の交流が促され、カルチャーやジャンルの境界線そのものを破壊していく役割も果たせる。この先にあるコンサートに向けて、コミュニティが次々に繋がっていくいい状態だと思います。
Q: 2018年にシンガポールで行われたTrue Colours Festivalは、1日だけのイベントでした。今回は2020年に向けて1年に渡ってイベントが続いていくわけですが、この期間の違いはどんな成果をあげると思いますか?
2018と2020では、そもそものメッセージが違います。2018のテーマは「障害」でした。舞台の上でパフォーマーたちがそれぞれの能力や才能を伝えていく中で、観客は彼らが抱えている障害を認識する、という期待がありました。合わせてワークショップや研究会も行いました。一方の2020では、より広いメッセージとして「人類の博愛(humanity)」「受容性(inclusion)」「アクセシビリティ(accessibility)」などが掲げられています。そういった大きなテーマを日本で伝えていくために、戦略的に長い期間を用意しました。日本では、TCFはまだ無名のイベントです。シンガポールでも最初は無名でしたが、シンガポールは小さい国ですから、最終的にはたくさんの人に知ってもらえました。日本はもっと広くて、様々な人たちが住んでいます。だから時間をかけてコンセプトを浸透させ、コンサートをやる頃には「TCFってこういうことなんだ」というメッセージが伝わっていて欲しいと思います。
主催の日本財団には「社会の変化に繋がるきっかけを作りたい」という思いがあると思います。シンガポールは建国時から多民族で形成されていて、人々はよくシンガポールはまるで多国籍企業のようだと言います。一方で日本はある意味で、単一民族的に構成されています。日本で多様性の問題、多様性の美しさを人々に伝えることは、社会的インクルージョン(受け入れること)への皮切りになるのではないかという思いに基づいて、2020は始動しています。

Q: 「他者を受け入れる仕組み」を作るためには、どんな観点が必要になってくると思いますか?
最初に私たちが学ばなければいけないのは、正常化する/普通にするということです。例えば、クラスや職場に障害のある人がいるのは特別ではなかったり、コミュニティやNPO・NGOで活動する時にLGBTの人がいることが普通であるという状況をつくらないといけない。世間ではふたつの相反する動きが起きています。ひとつはポピュラーカルチャーにおいて、多様性や違いを受け入れる動きです。一方でもともとそこに居る人たちが、自分たちの暮らしを海外から移住してくる新しい人たちから守ろうとする動きがあります。こういった守りの動きは、ポピュラーカルチャーの動きとは対立しているような状況だと言えます。
Q: 日本でもこの対立が入国管理センターでの在留外国人への対応の問題で明らかになったように思います。
入国管理センターが難民を犯罪者のように扱うのは、世界中どこに行っても同じ印象です。ただ、ひとつ共有したいことがあります。スリランカからの難民の方がディレクターを務める、インドの伝統的なダンスカンパニーについてです。そのカンパニーはとても革新的なテーマを扱うところで、彼らのダンス作品のなかに、UNHCRがだしているデータを使ったものがあったんですね。作中では地元の人たちは難民の人のことを自分たちの場所や仕事を奪っていく存在と感じていて、難民の方からみると自分たちは決してそこに居たいわけではなく、自分の国で職業や活動をしていたのに否応無くその国に来ている。その視点の違いが描かれていたんです。つまりもともとそこに居る人たちは、そもそも難民の方の意見を聞く機会がない。それはとても大事なことだと思います。
彼らがシンガポールで行った公演は多くの人に衝撃を与え、オーストラリアやイギリスなどいろんな国に招待されました。繰り返しますが、その作品はインドの伝統舞踊でありつつも、英語の副音声を使って、ある種普遍的な、いますべての人たちが体験しているテーマを扱っていて、そこでみんなが知らない難民の人たちの視点を伝え、それが見るものに非常に強いインパクトを与えたんです。この一連こそ、私はパフォーマンスの力だと思っています。
Q: 自分たちがもともといるスペースが侵食されていしまうという不安は、誰しもにあると思います。社会のなかで相手の視点に立つことは、どうすれば実現できると思いますか?
日常化する以外方法はないと思います。シンガポールも人口の約半分はシンガポールの市民権を持たない人たちです。それはシンガポール人の私にとって、居心地の悪い状況です。ただそういった状況であっても、無理をしてでも接点を持って、お互いにやりとりすることが必要だと思います。同じ市場で買い物するとか、日常での接点がないと、自分たちの環境のなかだけで過ごしてしまいますから。もちろん力づくで、ということではありません。ただ機会をつくることは重要で、同じ映画やパフォーマンスを見てそれぞれみんな違うけれど同じく感情的に高まって笑ったり泣いたり、そういうことを共有することが大切なのです。お互いへの理解は一夜にして得られるものではないですが、そうやって実は私たちの中身は一緒だ、ということを知り得る機会が日常の中にあることほど、良いことはないですね。
Q: 他者を受け入れることについてお伺いしましたが、逆に多民族国家シンガポールの人々は、自分のアイデンティティを大事にする・認めるという気持ちをどうやって育てているのですか?小学校の教育や思考の癖などに傾向があるのでしょうか?
非常に難しい問題ですね。シンガポールの独立は1965年で、日本のように何世紀もの歴史がある国ではありません。自国のアイデンティティを形成する前に、移住してくる様々な人たちと場を共有していく必要がありました。従って移民が多くいるということが、逆に自分たちがシンガポール人であるということを認識させてくれているとも言える状況です。
ただ中華系シンガポール人とインド系シンガポール人は、実は中国の人とインドの人よりも繋がりが強いといえます。中華系 / インド系といってもシンガポール人であることには変わりなく、その捉え方は移住してきたインド人や中国人たちとはかなり違います。教育というより、シンガポール人のものの考え方がそうなのかもしれません。
Q: True Colors Fetivalはコンサートを開催し、活動はフィナーレを迎えますね。コンサート実施以降は、社会はどんな風になっていると思いますか?
True Colors Festivalは正式には2018年に始まりましたが、それ以前から日本財団は違う名前でこのプロジェクトに取り組んでいます。先ほども言いましたが、1つや2つのフェスティバルで劇的な変化をもたらすのは難しく、いつもその過程でしかありません。長い旅路です。True Colors Festivalが終わった後も、そのメッセージは長く伝えられていく必要があるものです。True Colors Festivalが終わった後、こういったテーマやメッセージに対する社会的な見方は確実に変化するのではないかと思います。どのように変化していくのかも、私たちは調べ、見ていく必要があります。さほど大きな動きではないかもしれませんが、差別は減るし、相手を認めるとはいかずとも受け入れるという形で、変化していくものです。私たちが社会の分断を乗り越えるためには、その動きを推し進めるようなことをどんどん続け、そういったものがあちこちで見受けられるようにしていくことが大切です。

オードリー・ペレラ
True Colors Festival エグゼクティブ・プロデューサー
シンガポールを拠点にインディペンデントのフェスティバル・プロデユーサーとして活動。報道ジャーナリストを経て、世界最大規模のワールドミュージックの祭典「World of Music Arts & Dance (WOMAD) 」の企画とキュレーションに7年間従事。その後「The Ultimate Tribute Concert, Made in Singapore!」 や「Play It Back!」など国際的なポップアイコンによる音楽や、シンガポール独自の音楽とダンスの伝統を推し進めるようなフェスティバルを作り上げた。2016年、障害のあるアーティストたちの芸術祭「True Colours Festival Singapore」(主催:日本財団)のフェスティバル・ディレクターに就任。ワークショップ、トーク、ビジュアルアート、音楽など3日間のインタラクティブなプログラムの中で、20カ国から集まった200人以上の出演者がパフォーマンスを披露した。